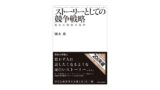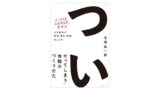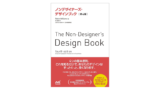『戦略ごっこ マーケティング以前の問題』(芹澤連)についての要約。
コトラーやアーカーなどのマーケティング書籍を中心に親しんできたため、本書で語られるエビデンスベーストマーケティングはかなり衝撃的だった。マーケティング業務に関わりながらも疑問に感じていた点が明らかになる爽快な一冊。
ひと言でまとめると
従来マーケティングで当たり前と思われていた常識/理論が実は研究データでは間違っていたということが多々ある。そのような事実に基づくマーケティング手法をエビデンスベーストマーケティング(Evidence-Based Marketing)と呼ばれ、本書ではマーケティングやブランディングのあたりまえを事実ベースで洗いなおしてみるという内容。
書籍のエッセンス
WHO
新規顧客vs既存顧客 どちらが大切か
どちらが大切ではなく、どちらも両方別々に対応する必要がある。ただし、成長に対するインパクトは「新規獲得>ロイヤルティ向上」である。
顧客関係管理にかかるコストは変動が大きく、新規顧客とほとんど変わらない、むしろ長期の顧客の方がコストは高くつくこともある。ロイヤル顧客の収益性がすべて高いわけではなく、収益性の高い顧客がすべてロイヤルなわけでもない。
離反はマーケターがコントロールできる変数ではない。離反も基本的にカテゴリーとそのブランドのシェアによって決まる(リテンションダブルジョパディ)。「離反を減らせば顧客数を維持できる」というロジックは逆で、正しくは「顧客数が増えることで相対的に離反率が減る」ということになる。
顧客ロイヤルティ
上位2割が8割の売り上げを占める…という話があるが、実際は50~60%程度にとどまる。
さらにヘビーユーザーの安定性(ある年の上位20%が翌年も上位20%に入る割合)は50%程度。1年で半分が入れ替わり、データ上はヘビーユーザーに見えても実際はライトユーザーという人が相当混ざっている。
同じ人でも時期によってヘビー/ライトを行ったり来たりするため、ヘビーユーザーだから購買頻度が高いのではなく、集計期間中に購買頻度が高かった人をヘビーユーザーとしてカウントしているだけ、という因果の向きが逆のパターンも十分あり得る。短期的に見ればヘビーユーザー/ライトユーザーでも長期的に見れば平均に回帰していく。たいていの場合短期的な動きを見るて間違ってカウントしていることが多い。
1年に1回以下しか購入しないウルトラライトユーザーが顧客の大半、かつ売り上げの半分近くを占めている場合も。小さなブランドでは顧客基盤に占めるウルトラライトユーザーの割合、売り上げ貢献が大きくなる。
離反は起こるものだと認めたうえで顧客にも見込顧客にも離反客にもリーチし、多くの人のレパートリーの中に入り続けること、レパートリー内でのセイリエンス(顕現性)を高め、需要が発生したときにブランドが想起される確率を増やすことが重要。
広告予算の配分比率
【消費財】長期的なブランド構築:60%、短期的な購買喚起に40%
【サブスク】長期的なブランド構築:74%、短期的な購買喚起に26% (Binet & Field, 2018)
態度変容/行動変容
通常、合理的行為モデル(熟慮行動理論) / 計画行動理論など、「態度変容→行動変容」と考えられがち。
一方日常におけるブランド選択はCEP(カテゴリーエントリーポイント:生活の中でカテゴリー需要が生まれ、その文脈に結び付いたブランドが想起される)の考え方が中心。
「喉が渇いた→ポカリスエットでも飲むか」とは思っても「ポカリスエットでも飲むか→喉が渇いてきた」とはならない。ジョブやニーズ、ゴールがあってこそブランドが想起されるというのが日常の自然な機序である。
アンケートでは具体的なジョブやカテゴリー需要が発生しているわけではないので、回答の理由になるのは過去の利用経験くらい。将来のブランド選択ではなく、過去の経験を思い出していることが多々ある。
「買わないといって買う人」と「買うと言って本当に買う人」の実数で考えると全社の方が大きい。
NPSの活用方法
・スコアの絶対値ではなく、スコアの変化に着目すること
・既存顧客のスコアだけでなく、見顧客を含めた全員のスコアを使うこと
・四半期程度の短期の予測にとどめること
WHAT
差別化
差別化だけで成長できるわけではない、必要条件ではあっても十分条件ではない。
ほとんどの人はブランドが「差別化されている」とは思っていない、それにも関わらず買っている。普段の感覚で見れば大した差はない。
価格戦略
大きなブランドは価格弾性力が低く、小さなブランドは大きい。
「何に対して」「どんな時に」財布のひもが緩むのかを考える必要がある。
同じ人でも文脈やオケージョンに応じて価格感度が変わる。カテゴリーエントリーポイントやジョブ理論的な視点が重要
値上げ/値下げでは主要な競合の価格を通り越す価格変更をした場合に弾性力に大きな変化が起こる。
価格プロモーションに反応するのは主に既存顧客やカテゴリーヘビーユーザーで、新規獲得の効果はあまりない。
商品戦略
HOW
STP、ブランドイメージ、パーセプション
ブランドイメージもダブルジョパディの法則にしたがう。大きなブランドはどんなイメージも高く、小さなブランドはどんなイメージも低くなっている。個々のマーケティング活動ではなく浸透率やシェアと連動する。
独自の位置づけという幻想
差別化することで「このベネフィットが得られるのはこのブランドだけ」という説得力が備わり、ブランドを買うべき理由を生み出す。同時にそうしたイメージが競合に対する優位性となり、消費者の中で独自の位置づけ、ポジショニングが確立される…というのはまやかし。
ファクト
・顧客の大半は差別化されていると思っていないしそう思わなくても買っている
・消費者がブランドをその属性と結びつけるかは確率的に変わる
・既存顧客には有効な面もあるが、未顧客には別の切り口が必要
買う理由で購買行動が起こるのは一部の既存顧客やヘビーユーザーであり大半の消費者は買う理由/買わない理由は考えていない
・どこと競合になるかはポジショニングではなくシェアで決まる。
ブランドが成長するときは特定のターゲットのセグメントだけではなく、あらゆるセグメントから新規顧客を獲得して成長している。STPのロジックで成長しているわけではない。ポジショニングではなく間口の広さで成長している。未顧客の獲得に必要なのは1つの強いポジショニングではなく、薄く広いパーセプション。
ブランドの一貫性に関して、CEPを増やしても消費者は混乱しない。懸念点としては、広告予算が分散され各々の広告規模が小さくなること
1つのオケージョンである程度の想起を獲得したら別のオケージョンでの想起獲得に取り組むべき。パーセプションの強さよりも、広さが重要。
CEPの平均は6.4個、CEPが1つしかない人は1~2割程度
結びついているCEPや属性の数とブランドの成長の間には強い関連があり、ブランドと結びついたCEPの数を増やしていく、ブランドとCEPの結びつきを強めていくことが重要
CEPを探す
W’s フレームワーク
Why:なぜそのカテゴリーを使うか、どんなゴールのために採用するのか
When:カテゴリーを購買/利用するのは一日の中でいつか、シーズナリティ、いつもの行動が変わるときはどんな時?
Where:どこで利用されるか。リアル/デジタルの区分。いつもと違う場所で利用することはあるか
While:カテゴリーを利用する前後は何をしているか、どんな行動の最中にニーズが生まれるか
with/for What:そのカテゴリーを使う時に、他にどんなカテゴリーを同時に利用するか、カテゴリーが利用できないとき何で代用するか
with/for Whom:買うのは誰で利用するのはだれか、利用するときに誰がいるか、行動に影響を与える第三者
How feeling:カテゴリーの利用前後での気分の変化
購入時の前後文脈を状況的な手掛かりとしてメッセージやクリエイティブの中に配しておく
メディアプラン/クリエイティブ
マーケティングコミュニケーションの主な働きは、「ブランドに関する記憶や連想をリフレッシュすることで、購買時に想起されやすくする」というセイリエンスである。
購買ファネルという錯視
ファネルは消費者行動やカスタマージャーニーではない。ファネルは企業側の管理ツールであり歩留まりは集計ロジックに過ぎず、その発想自体がそもそもずれている。
広告予算、ROI
限界利益:売上-変動費
ブランドの限界利益率が50%だとすると、100万円の広告費をペイするためには最低ども100万円/50%≒200万円の売上が必要
小さなブランドが現在の市場シェアを安定して維持するためには市場シェアと同等以上の広告量が必要
ROIは効率の指標であって効果の指標ではない
効率を優先するとマーケティング活動が小規模になり結果的にリターンの是たち額も小さくなっていく
MROI= (マーケティングに起因する増分売上× 限界利益率or粗利率 – マーケティング費用)/マーケティング費用
3つのROI
トータルROI:すべてのコストとそこから得られたすべてのリターン
インクリメンタルROI:ある時点から追加で行ったマーケティング活動に対して追加で得られた増分リターンがいくらなのか
マージナルROI:広告をわずかに増やしたときに売り上げがどれくらい増えるのか
メディアプランを考える際には次に出すならどの媒体に出すとROIが高くなるのかというインクリメンタルの視点が重要になる。
用語
ダブルジョパディ(Double Jeopardy)の法則
日本語に訳すると「二重の不利」となり、「浸透率と購入頻度には正の相関関係がある」という法則。逆を言うと「浸透率の低いブランドほど、購入される頻度も少なくなる」という二重に不利な状況になる。
本書の各所で語られる重要な法則
SCR(Share of Category Requirements)
顧客の特定期間におけるブランド購入数/糧えごりー購入数。日本だとウォレットシェア(財布内シェア)といわれることも
CEP(Category Entry Point)
ブランドを選ぶ前に形成され、購買の選択肢を与えるきっかけとなる試行。普段の生活を送っている中で何らかのニーズやジョブが発生し、「日常モード」から「カテゴリー購入モード」に代わる。CEPはそのきっかけとなる試行や文脈。
水平的差別化と垂直的差別化
水平的差別化
人の好みや評価が分かれるような属性(水平的属性)についての差別化
・人によって好みや評価が分かれるような属性の差別化
・特定の利用やオケージョンや顧客セグメントの効用を高める
・価格帯はほぼ同じだが、競合hにはない機能や性能を備える
・主に既存顧客やヘビーユーザーのWTPを高める
・マーケティングやブランディングによるパーセプション上の差別化
→マージン成長に貢献
垂直的差別化
そのカテゴリーに共通して求められる基本的な品質(垂直的属性)についての差別化
・カテゴリーユーザーすべてに好まれるような品質の差別化
・プレファレンスによらずすべての顧客の効用を高める
・どのブランドも備えている属性だが品質や価格が異なる
・ブランド非購買者を含め、カテゴリーユーザー全員のWTPを高める
・技術革新や研究開発による性能向上、イノベーションに近い場合もある
→ボリューム成長に貢献
記述属性と評価属性
評価属性:カテゴリーのどのブランドにも当てはまり、消費者がブランドを評価する際に一般的に用いる価値判断を評価属性
→シェアや利用経験と連動し、未顧客への訴求軸にはなりにくい
記述属性:特定のブランドに固有の特徴や重点的にマーケティングされている機能に対するパーセプション
→必ずしも顧客数や利用経験と連動せず、未顧客への訴求軸になりえる
リトリーバルデザイン
記憶と早期の特性に基づいて文脈単位の早期をデザインすること
PODとPOP
POD(Point of Difference):相違点連想
POP(Point of Parity):類似点連想
PODの前にPOPを達成することが大切。「どこが違うか」の前にまず「何であるか」が先である
セイリエンス
ブランドに関する記憶や連想をリフレッシュすることで、購買時に想起されやすくすること